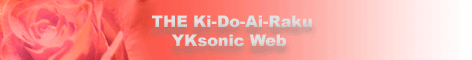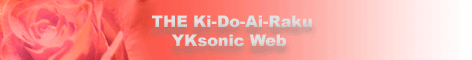| とにかく予約が取りにくくなった。ランチタイムは特に人気があり、とりわけ土曜日は三ヶ月前の受付開始日の午前中にはほぼ一杯になるという。週末のディナーも確保できたとすれば相当ラッキーだ。高級店はどこも苦戦しているというのに、これだけ人気があり、繁盛しているのは素晴らしいことだと言えよう。今回は週末に継続的に席を確保している方の厚意で、予約を譲っていただいた。
店先には二人の駐車場係、一人のドア係が立ち、エントランスを入ると三人のレセプショニストとメートルドテルが出迎えてくれる。メートルドテルに先導されて、階上のダイニングへと進む。途中「先にトイレに行きますか?」とストレートな表現で尋ねられたが、もう少し含みのある言い回しができないものかと僅かに違和感を覚えた。ダイニングホールはすでに満席の賑わいだった。二人連れが8組、そして6人のグループ、4人、3人・・・反対の個室にも6人くらいいるだろうか。すべてあわせても40名程度と、パリの人気店のように、ぎゅっと凝縮したようなイメージだ。アペリティフを注文してから、メニューが渡されるまで、思いのほか間があったので、店内の様子をしみじみと観察した。インテリアはモダンだが上質。華やかではないが、キラリと光るエッジがある。また、店内は明るく、身に着けているものがよく映える。
料理はアラカルトで注文した。前菜、魚、肉と欲張ったが、さすがにすべて通常のポーションではきついと思い、魚はハーフポーションにしてもらった。正確にはハーフではなかったが。魚料理は帆立貝を選んだのだが、注文の際、1人前だといくつ載っているのかと尋ねると、係は自信を持って6個だと答えた。なら半分の3個でいいと思ったわけだが、後になって実は1人前で3個だと訂正しにきた。間違えたのに、決して詫びらしき言葉を口にしないのも気に障ったが、せっかくの食事をまずくしたくないので、黙って聞きながら、3分の2にしてくれるよう頼んだ。
前菜のグルヌイユは素晴らしかった。軽く揚がり、アイユのピュレとも相性がいい。アスパラガスが添えられた帆立もまた申し分なかったが、メインディッシュの蝦夷鹿は、肉そのものの旨みに欠け、添えられたトリュフもまったく香らず、その芳香はメートルドテルの仄かな香水にさえ敵わなかった。その前の二皿があまりに素晴らしかったからかもしれないが、メインディッシュへの期待が高まっていた分だけがっかりした。それに、この季節に香るトリュフを期待するのは、時期尚早かもしれない。
ワインはシェフソムリエの勧めに従って選んで正解だった。豊富な知識と、いたずらに高価なものを押し付けない姿勢に、安心して信頼を寄せられる。しかし、その他のサービス陣にはいささか不満が残った。最初にエビアンの大瓶を頼み、最初の一杯がグラスに注がれたきり、空になっても注ぎ足されることがなかった。自分で注ごうにも一体ボトルはどこへ行ってしまったのか見当たらない。食事が終わってから、もう一本持ってくるかと尋ねられるまで、水のグラスは空のままだった。もう一本注文したら、今度はどこからともなく、最初のボトルが現れ、結局会計でもエビアンは1本だけが計上されていた。全体的に、わずかながらタイミングを逃すことが多く、グランメゾンのサービスとしては満点をつけるわけにはいかない。
聞くところに寄れば、この地の「ロオジエ」は資生堂パーラーの上にあった時とは路線を違え、初めてこの店を訪れるゲストにも、足繁く通う常連にも、くつろいだ雰囲気の中で最高の食事を楽しめるよう心がけているという。そのため、威圧感のあるようなサービススタイルは敢えてとっていない。だが、気取ったサービスをするよりも、親近感と節度のバランスがとれたサービスをする方が難しい。困難なことゆえに、給仕によってはそのテクニックを自在に操るまでに至らないばかりか、何かしらの勘違いがあるようにも見受けられた。
しかし、店全体を包み込む活気ある空気そのものが、この店の比類なき実力を物語っていることも確かだった。見渡せば、ほとんどが常連客であるかのように見える。なぜなら誰しもが本当に楽しそうに「ロオジエ」での時間を満喫しているからだ。今回は多少の不満はあったものの、それでも、この国でこれ以上を望むのは困難だと思われる。「本物は、古い新しいという概念を越え常にモダンでエレガントなもの」というジャック・ボリー氏の哲学には、心底共感を覚える。
|